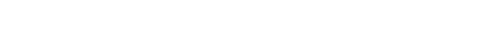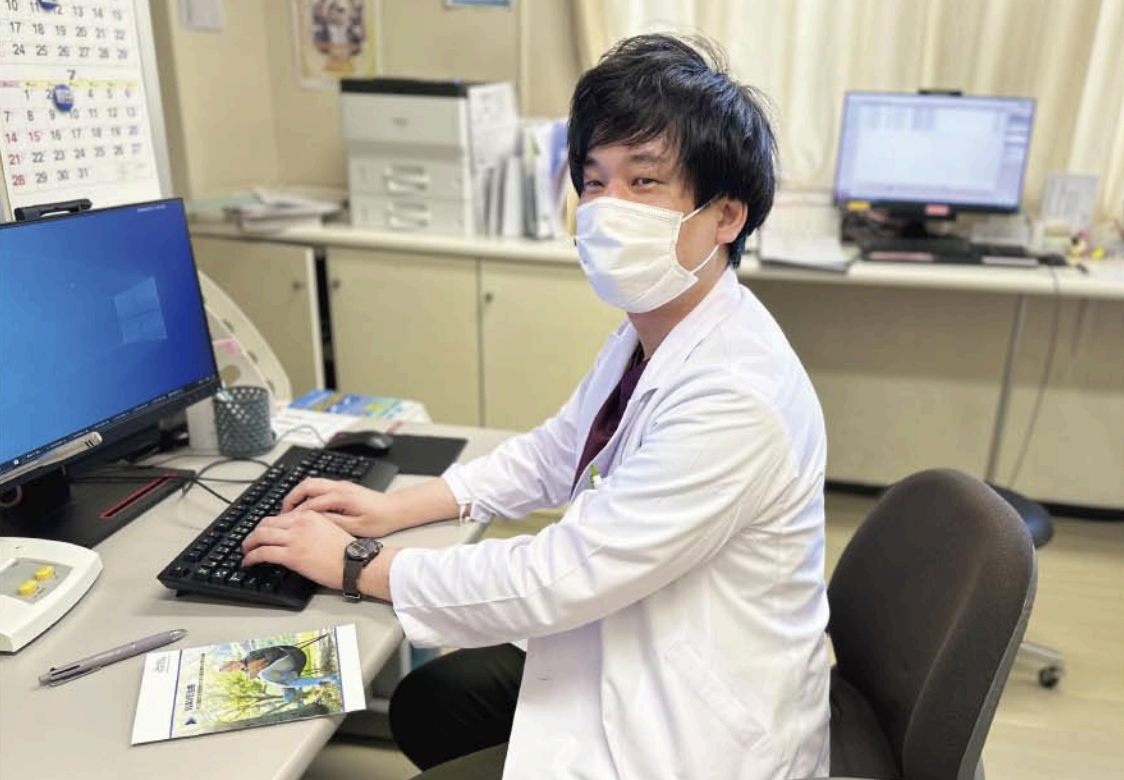医療安全について秦誠宏副院長にお話をうかがいました
※この記事は院内誌Human2019年7月号で紹介された過去の記事です
「医療安全」とか「医療事故」とか聞くと、どんなイメージを持ちますか?「あー、どこかの大きな病院が医療ミスで〇〇万円払ったとか新聞に出てたわ」など思われるかもしれません。ここで確認しておきますが、医療事故と医療ミス(過誤)は違います。確かに、医療ミスが原因の医療事故もありますが、医療ミスがなくても医療事故は起こることがあります。例えば、今までアレルギーの無かった人が急に薬のアレルギーで蕁麻疹が出たり(薬疹と言います)、お元気な方でも病室で転倒して骨折したりする事があります。必ずしも、ミスがなくても事故は起こるのです。
1999年1月11日、日本の医療の信頼を揺るがす、重大な医療事故が起きました。横浜市立大学病院で起きた、手術患者のとり違え事故です。同じ年の2月11日には都立広尾病院で消毒薬の注射事件が起きました。この年から日本の医療安全に対する取り組みが進んで来ました。病院の医療は安全であると思われていましたが、病院でも間違いが起きると言う事が認識され、現状を把握するために、報告をする事が、義務付けられて来ました。
病院では、どんな些細なことでも、患者さんに悪影響があった、或いは悪影響が出る可能性があったことは有害事象として、報告されています。さくら総合病院でも、毎月100件以上の有害事象が報告され、年々増加してきています。そんなに問題が起きているのか、どんどん増えていると言うのはどう言う事?と驚かれるかもしれません。これは、職員の安全意識が向上してきているためと思われます。問題と思われていなかった事が、問題として認識されるようになってきた結果、報告が増えてきているのです。
有害事象のうち、患者さんへの影響度により、ヒヤリハットと事故と分けています。患者さんへの影響が少ないものはヒヤリハット、大きいものは事故として扱います。軽微な有害事象の原因を調査し、重大な事故を防ぐための努力をしています。
交通事故では、事故の原因追求のため警察が調査します。病院内で起きた有害事象は、医療安全管理室で調査をします。重大な事故の時は医療事故調査委員会にて調査します。
医療法の改正により、平成27年10月より新しい「医療事故調査制度」が施行されました。ここで言う医療事故の範囲は、「医療従事者が提供した医療に起因し、または起因すると疑われる死亡又は死産」で、「当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの」です。これに該当するものは、医療事故調査・支援センターに報告する必要があります。院内での調査が困難であったような場合には、医療事故調査等支援団体に必要な支援を求める事があります。
我々も、安全な医療を提供するために日々努力しておりますが、患者さんにも是非、協力をお願いしたいと思っています。まず、外来受診時には、診察室に入ったら名前(フルネームで)と生年月日を言ってください。外来で診察を受ける患者さんは多数いて、電子カルテでは開いているカルテと目の前にいる患者さんが同じかどうか、わからない事があります。同姓同名の患者さんもいますので、生年月日まで言ってもらうと間違いがかなり減ると思います。検査を受ける時も、名前を言ってください。レントゲンを撮る時は、何処が痛くて検査を受けるか担当技師に伝えてください。手術を受ける時には、十分な説明を聞いてください。手術室に入る時も名前と生年月日、どこの手術を受けるか、右・左まで言ってください。
より安全な医療を受けるために、患者さんとご家族のご理解・ご協力をよろしくお願い致します。
日本脊髄外科学会認定医
愛知県救急業務高度化推進協議会指導医
所属学会
日本脳神経外科学会
日本リハビリテーション医学会
日本脊髄外科学会
日本ボツリヌス治療学会
日本脳神経外科漢方医学会
日本脳神経外科コングレス
日本てんかん外科学会
日本脳卒中学会
日本臨床脳神経外科学会