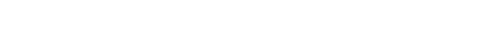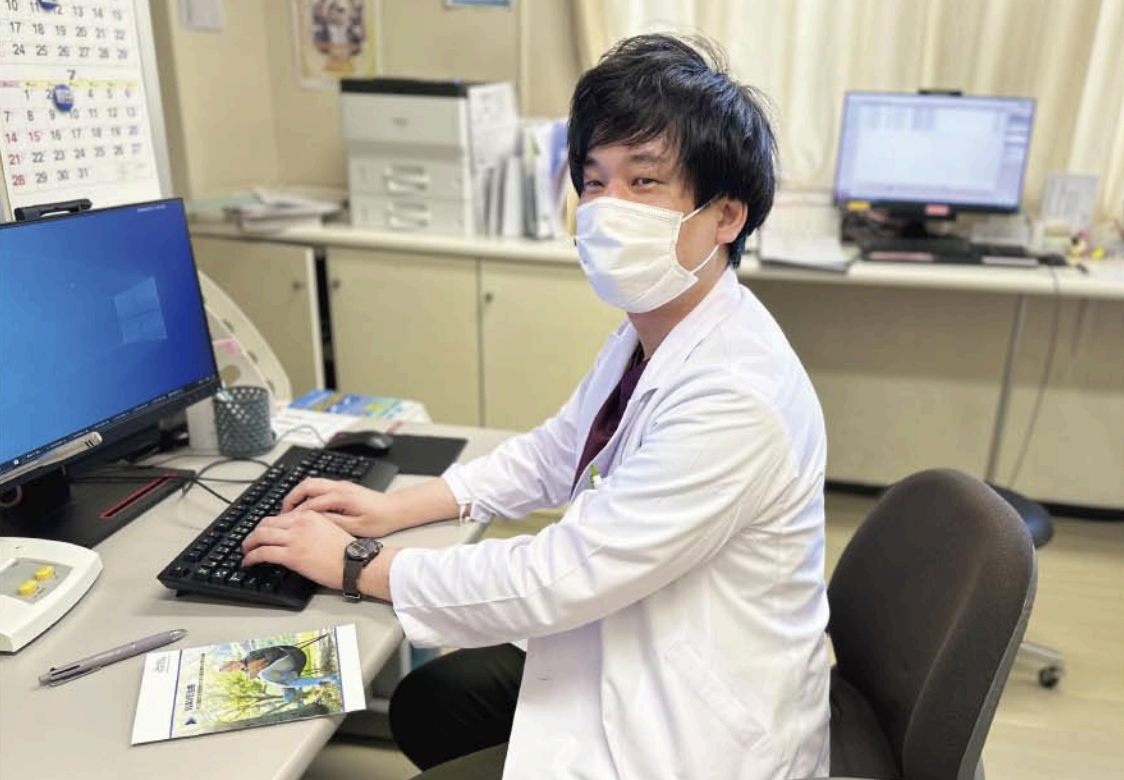秦誠宏副院長にお話をうかがいました
※この記事は院内誌Human2016年8月号で紹介された過去の記事です
脳神経外科では主にくも膜下出血、脳出血、脳梗塞といった脳血管障害や、脳腫瘍、頭部外傷を主に治療しています。当院では、さらに頚椎症、腰部脊柱管狭窄症、頚椎・腰椎椎間板ヘルニアなどの脊椎脊髄疾患も積極的に治療しています。
他にパーキンソン病やてんかん、三叉神経痛、顔面痙攣といった、機能的脳神経外科の治療も行ないます。脳腫瘍やくも膜下出血のように、生命に関わるような器質的疾患ではなく、痛みや、運動機能に関する疾患に、神経機能の障害を改善する目的で手術などの治療を行ないます。
三叉神経痛は顔の痛み、顔面痙攣は顔の筋肉が痙攣してしまう病気です。これらには微小血管減圧術という手術を行ないます。これは、頭蓋内で、三叉神経や顔面神経を動脈が圧迫することによって顔の痛みや顔の痙攣が起こるため、神経から動脈を離す手術を行ないます。顔面痙攣に対してはボツリヌス療法を行なうこともあります。ボツリヌス療法については後述します。
パーキンソン病は神経難病の一つで、進行性に体が動かしにくくなったり、手が震えたりする症状が悪化していきます。
病初期はL-DOPAなどの抗パーキンソン病薬が効きますが、病気が進行するにつれて、薬が効きにくくなったり、効いている時間が短くなったりします。病気が進行してきたときには定位脳手術による治療を行ないます。定位脳手術はCTやMRIの画像を元に、脳の特定の部位を破壊したり、刺激する電極を埋め込んだりします。本態性振戦など、他の不随意運動にも有効なことがあります。
てんかんに対しては焦点切除や、側頭葉切除などを行ないます。薬物のみで治療が困難な、難治性のてんかんに対し、手術を行ないます。
定位脳手術やてんかんの手術は特殊な機械が必要で、また、手術前の評価が重要なため、大学病院など、一部の病院で行われています。
当院では難治性疼痛に対する、脊髄刺激療法や、痙縮に対するバクロフェン髄注療法、ボツリヌス療法を行なっています。
脊髄損傷や、脳卒中後、などに難治性の神経痛が生じることがあります。薬物療法でも疼痛のコントロールが困難な場合に、脊髄刺激療法を行ないます。痛みの強い部位に合わせて、頸部や背部から脊椎の中に電極を挿入し、脊髄を刺激します。電極は脊椎の中ですが、神経を包んでいる硬膜の外に留置します。刺激する機械は腹部または臀部の皮下に埋め込みます。刺激の強さや刺激の仕方は皮下に埋め込んだ機械を体外から調整することができます。痛みを完全に取り去ることはできませんが、ある程度和らげることができます。最近、下肢の閉塞性動脈硬化症に対する効果もあることが分かってきました。
脳卒中や脊髄損傷後に四肢の麻痺が残ることがあります。また、麻痺した手足に痙縮と言って筋肉の強張りが生じることがあります。この痙縮に対し、ボツリヌス療法や、バクロフェン髄注療法を行ないます。
ボツリヌス療法はボツリヌス菌が産生する毒素を使用します。ボツリヌス菌そのものを注射するわけではありません。こわばった筋肉に直接薬を注射します。薬の効果は約3ヶ月持続します。3ヶ月で効果が切れるので、3ヶ月毎に注射する必要があります。一回に使用できる薬の量が決まっているため、こわばっている筋肉が多い場合には不適です。前述した顔面痙攣、眼瞼痙攣にもボツリヌス療法を行ないます。最近は腋下多汗症にも保険適用になりました。
痙縮が強い場合や、痙縮している筋が多い場合にはバクロフェン髄注療法を行ないます。腰から脊椎の中にカテーテルという管を挿入し、ポンプを腹部に埋め込みます。脊髄刺激療法の場合は硬膜外に電極を留置しますが、バクロフェン髄注療法のカテーテルは硬膜内(神経の入っている場所)に留置します。バクロフェンという筋を弛緩させる薬が持続的にポンプから少しずつ髄腔内に注入されます。注入される薬の速度は体外から調整することができます。薬の注入する速度にもよりますが、約3ヶ月で薬がなくなるため、3ヶ月毎に薬を補充する必要があります。ボツリヌス療法もバクロフェン髄注療法も麻痺が治るわけではありませんが、痙縮による日常生活上の障害の改善には有効です。
強い神経痛や痙縮、顔面痙攣でお困りの方は脳神経外科でご相談ください。

日本脊髄外科学会認定医
愛知県救急業務高度化推進協議会指導医
所属学会
日本脳神経外科学会
日本リハビリテーション医学会
日本脊髄外科学会
日本ボツリヌス治療学会
日本脳神経外科漢方医学会
日本脳神経外科コングレス
日本てんかん外科学会
日本脳卒中学会
日本臨床脳神経外科学会