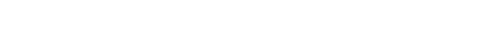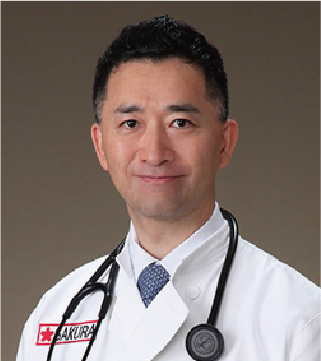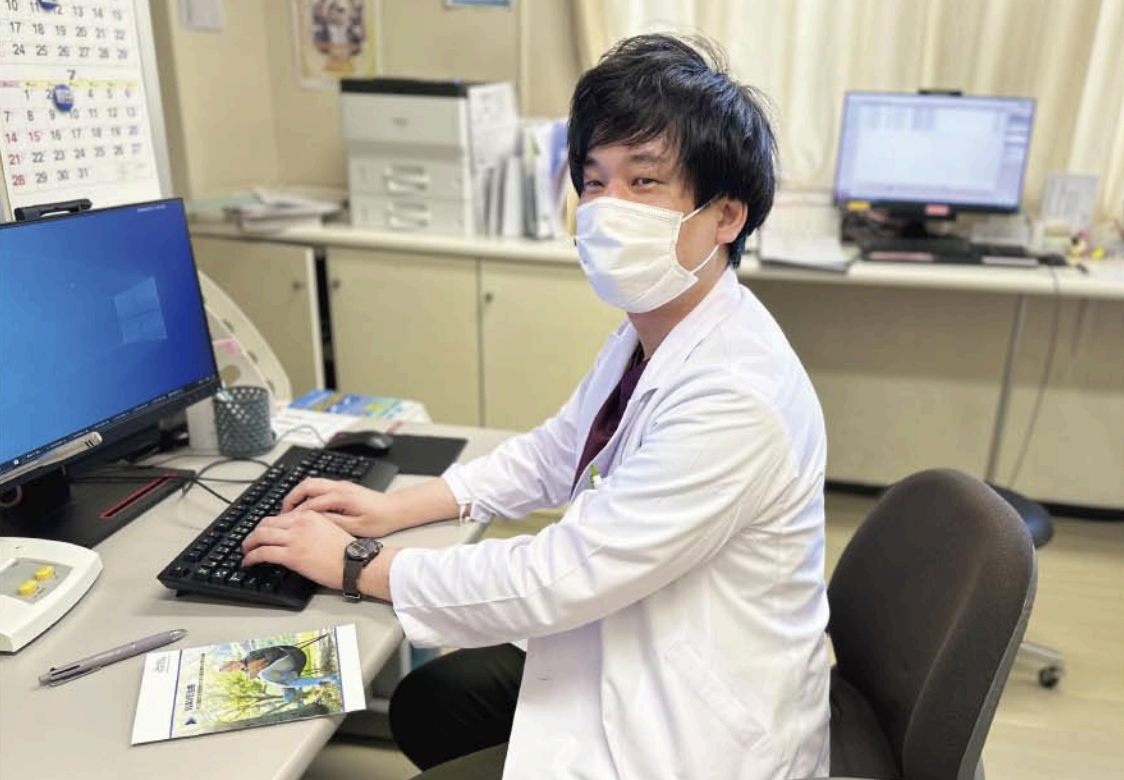熊本地震災害医療救援について小林豊病院長に話をうかがいました。
※この記事は院内誌Human2016年6月号で紹介された過去の記事です
当院から900㎞離れた熊本で、その地震は4月14日に発災した。震度7と聞いた時、阪神淡路大震災や東日本大震災の超急性期に医療救援隊として現地に入った時の記憶が蘇った。「行かなければいけない」と反射的に浮かんだ。しかし、行けなかった。900㎞離れた田舎で大切な職員を引き連れて無事に帰ってくることができるのか、不安だった。そんな迷いの最中に4月16日に、後に本震と評された2回目の震度7が起きた。新たな大きな被害は無いようであったが、類い稀な震度7が2回という事実以上に、一向に収まる様子の無い余震は、被災者に長期の避難所生活を余儀なくさせるには十分なものであった。
本職である外科医としての貢献は、発災後72時間というタイムリミットがあり、900㎞という距離が我々にそれを許してくれなかった。しかしながら、収まらぬ余震に伴う医療ニーズとゴールデンウィーク前という医療ボランティアの不足したタイミングが我々の背中を押す形となった。
4月24日朝7時に多くの職員に見送られながら、私以下9名(医師1名、看護師2名、薬剤師1名、放射線技師1名、広報課事務員1名、医事課事務員1名、車輌課運転士2名)で緊急車両2台に支援物資満載の状態で赤レンガを後にした。隊員全員交代交代で運転し、熊本県阿蘇にある阿蘇医療センターに到着したのは13時間後の夜8時であった。門を叩いたのは、阿蘇医療センターに開設間もない各医療救援隊の統括管理する組織(阿蘇地区災害保健医療復興連絡会議Aso Disaster Recovery Organization:ADRO)であった。我々が移動を含めた7日間活動する決意を伝え、20㎞離れた古い公民館を雨風凌げる住処として提供された。水道も電気も通った公民館は、毛布一枚にくるまって眠る環境でも、車中泊を覚悟していた我々には短い期間の我が家になった。

我々に割り当てられた任務は「感染管理」である。各避難所で多くの高齢者が劣悪な環境での集団生活を余儀なくされており、体力や抵抗力の落ちた被災者の中での感染症の発症は、災害後のこの時期の最重要課題であった。水が流れないトイレや炊き出しの配給、手指衛生の欠落や環境清浄の不足など30か所近くの各避難所の現状を感染管理の観点から調査し評価して、長崎大学感染制御教育センター泉川教授率いる感染管理本部(阿蘇医療センター内)へ報告する。この報告を感染管理本部が解析して感染のリスクを分類し対策を立てる。我々はこの結果をもって、各避難所へ赴き、感染管理のための指導・教育と感染管理関連物品の配布を行なった。私が感染管理医師(Infection control doctor)の認定を持っていたことも役に立った。また急性疾病の発生により要請を受けて、避難所で診察と必要に応じた隔離と治療を行なった。通常、ノロウイルスもインフルエンザウイルスも珍しい病気ではなく、多くは対症療法で十分治癒が期待できる。しかしながら、被災者の生活環境を考えると、一度このような感染症が発生すると、重症化しやすいばかりでなく、避難所の特性から、一気に多くの傷病者が発生する可能性が高い。ただでも災害により医療の提供体制が揺らぎ、医療従事者も疲弊している中で、このような多数の傷病者による医療ニーズの増大は提供できる医療のキャパシティーを大きく超え、脆弱化した医療体制が瞬時に破綻しかねない。この状況下では予防と感染症の囲い込みがこの地域の医療を支える鍵となるのである。我々はその鍵の一つを任されるという大役を粛々とこなすのであった。
予定された日程と与えられた任務を完遂し、阿蘇医療センターを後にした。阿蘇で活動を開始した時、道行く車両は自衛隊車両がほとんどであった。しかしながら我々が後ろ髪引かれる思いで阿蘇医療センターに背をむける頃には、一般車両がだいぶ増え、逆に自衛隊車両がまばらになっていた。この変化こそが災害後急性期の一段落を物語っていた。1週間の非日常的かつ厳しい環境での生活を文句一つ言わずに過ごした当院の隊員は疲労の影も見せなかったが、隠れた疲労に隊員の健康(一番は自分の健康か)を危惧し、復路は大分から神戸までフェリーを利用した。フェリーの中で1週間ぶりに温かい食事を摂り、風呂やシャワーを浴び、肩幅ほどの大きさではあるものの布団の上で眠る隊員の寝顔は安堵を感じさせるものであった。29日の朝に赤レンガに帰還。理事長以下、多くの職員やテレビの取材に出迎えていただき、隊員全員が体調を崩すこともなく笑顔で任務を完了したことに、喜びと感謝の気持ちでいっぱいであった。我々の活動は1週間で終わりを告げたが、被災者の方々の不自由な生活や精神的負担はこれからも続き、いつ終わりを迎えるか知るものはいない。1日も早い復興は、病院一同の大きな願いである。熊本への熱い想いを胸に、この地域における医療に真摯に取り組むことが、唯一我々にできることであろう。
日本外科学会専門医
日本消化器外科学会専門医・指導医
日本消化器病学会専門医
日本消化管学会胃腸科専門医
日本救急医学会救急科専門医
日本大腸肛門病学会専門医
日本腹部救急医学会認定医・教育医
消化器がん外科治療認定医
国立がん研究センター中央病院外科レジデント・がん専門修練医修了
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
日本医師会認定産業医
日本禁煙学会認定指導医
日本救急医学会ICD(Infection Control Doctor)
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
日本法医学会死体検案認定医
愛知県医師会検視立会医
愛知県救急業務高度化推進協議会指導医
四段階注射法講習会受講修了